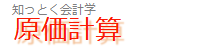直接原価計算と価格決定
製品の価格決定に対する態度の表明を価格政策といいます。そして、価格決定とは、価格政策を前提にした価格の意思決定を意味します。
企業の販売価格は、利潤追求などの企業目的の達成に必要な基本的要因の1つです。価格決定のいかんによっては、企業の存否を決定づけることもあります。
そのため、経営者は、企業の経済理論、会計学、マーケティング、経営学の知識をもとに適切な価格設定を行わなければなりません。
ここで、企業の経済理論によれば、市場価格は、需要曲線と供給曲線の交点で決まるとされています。そして、分析の前提に利潤極大化が置かれています。
しかし、企業の経済理論には、以下の限界があるため、企業の価格決定に利用するのが困難です。
- 現実の経営においては、企業の社会的責任など多種の目標を勘案しながら適正利益の獲得を行わなければならず、利潤極大化だけを追求すれば良いわけではない。
- 限界収入曲線や限界費用曲線などを経営者が把握するのが困難である。
- 経済モデルは単純化され過ぎているため、実際に適用するのが難しい。
一方、会計モデルでは、原価の果たす役割を重視し、原価を中心にして価格決定が行われます。
原価を基礎にした価格決定には、大きく分けて、全部原価法と部分原価法があります。
全部原価法
全部原価法は、製品または用役の単位当たり全部原価を計算し、これに一定の利益を加算して目標価格を決定する価格決定の方法です。計算式は以下の通りです。
- 目標価格
=製品単位当たり総原価+製品単位当たり目標利益
総原価は、製造原価だけでなく販売費および一般管理費も加えた原価です。
例えば、製造原価と販売費および一般管理費が以下のように予測されていたとします。
- 直接材料費=30円/個
- 直接労務費=10円/個
- 変動間接費=4円/個
- 固定間接費=6円/個
- 変動販売費=2円/個
- 固定管理費=4円/個
- 総原価=56円/個
この場合、総原価に対して25%の目標利益を付加して販売するなら、目標価格は70円になります。
- 目標価格
=56円+56円×25%
=70円
全部原価法の長所
全部原価法による価格決定には、以下の長所があります。
- 価格決定の出発点となる
- 長期的視野に立った価格決定
- 社会的承認が得られる
価格決定の出発点となる
製品価格と需要量との関係が明確でない場合、顧客の反応を確認しながら試行錯誤的に価格の修正を行う必要があります。
そのためには何らかの基準が必要ですが、全部原価は価格決定の出発点として選ばれやすいと考えられます。
長期的視野に立った価格決定
全部原価法では、固定費の配賦額も含めた総原価の回収と目標利益の獲得が図られるので、長期的視野に立った価格決定が可能になります。
社会的承認が得られる
全部原価の回収と適正利益の獲得は、企業の価格決定に正当性を与えるので、社会的承認を得られやすい面を持っています。
全部原価法の短所
上の例で、操業度が半分になったと仮定します。この場合、製品1個あたりの固定費の配賦額は2倍に上がりますから、固定間接費は12円/個、固定管理費は8円/個の配賦額になります。したがって、総原価は66円/個です。
総原価が66円/個と、当初より10円高くなっても、目標利益を総原価の25%とした場合、目標価格は82.5円になります。
- 目標価格
=66円+66円×25%
=82.5円
操業度が半分になったのが、製品の需要が落ちたことが理由であれば、製品の値上げは逆効果です。
本来、売上が落ち込んだ場合には製品価格を低く設定すべきです。また、売上が好調な場合には、製品価格を高く設定できます。
しかし、全部原価法では、生産量の増加に伴い、製品1個あたりの配賦固定費が下がるため、目標価格が低く設定されてしまいます。反対に生産量が減少すると、配賦固定費が上がり、目標価格が高く設定されてしまいます。
このように全部原価法では、販売価格が全部原価を上回らなければならないと考えているため、価格決定が硬直化し非弾力的なものになる欠点を持っています。
また、共通固定費の配賦基準が合理的でない場合には、原価の信頼性が下がり、個々の製品の収益性が不明確になる短所もあります。
他に全部原価法での価格決定は、販売価格以上で販売している限り原価の回収ができているとの誤った安心感を与える危険もあります。
加工費法
全部原価法の変形に加工費法があります。計算式は以下の通りです。
- 目標価格
=製品単位当たり総原価+加工費×目標利益率
総原価が56円、そのうち加工費が10円だった場合、加工費の50%の利益を上乗せするとすれば、目標価格は61円になります。
- 目標価格
=56円+10円×50%
=61円
投資利益率法
投資利益率法も全部原価法の一種で、以下の計算式で目標価格を決定します。
- 目標価格
=製品単位当たり総原価+目標投資利益率×投資額/製造販売量
総原価が56円、目標投資利益率が10%、投資額が1,000,000円、製造販売量が10,000個だった場合、目標価格は66円になります。
- 目標価格
=56円+10%×1,000,000円/10,000個
=66円
部分原価法
部分原価法は、販売される製品の部分原価を計算し、これを基礎にして目標価格を決定する方法です。部分原価法で利用されやすいのは直接原価基準です。
直接原価基準による目標価格の計算式は以下の通りです。
- 目標価格
=製品単位当たり変動費+製品単位当たり限界利益
=製品単位当たり変動費/(1-限界利益率)
直接原価基準の長所
このページの最初の例では、製品1個あたりの総原価が56円、変動費が46円、固定費が10円でした。
もしも、ある顧客から1個50円で販売して欲しいとの注文を受けた場合、全部原価を基準にすれば、総原価が56円なので、1個あたり6円の損失となり、この注文を断ることになります。
しかし、直接原価基準で目標価格を設定している場合は、変動費が46円なので、50円での受注は1個あたり4円の限界利益を増やし、固定費の回収に貢献するので、この注文を受けるべきとの意思決定をします。
このように直接原価基準によって価格決定を行うと、各製品の限界利益(貢献利益)によって、どれだけ固定費を回収できるかがわかりやすくなり、各製品固有の収益性が明確となります。
そのため、各製品の収益力に応じて固定費を回収し利益獲得に貢献できる価格を弾力的に決定可能です。
そして、直接原価基準での価格決定では、製品単位当たりの限界利益率を把握できるので、CVP分析が可能となる長所もあります。
直接原価基準の短所
しかし、一方で、直接原価基準による価格決定には以下のような短所もあります。
- 全部原価が回収されない危険性
- 長期的に競争を激化させる危険性
全部原価が回収されない危険性
直接原価基準に関わらず、部分原価法では、価格決定の基礎となった部分原価だけが回収されれば良いと理解されやすく、固定費も含めた全部原価を回収できる価格よりも低い価格を設定してしまう危険があります。
長期的に競争を激化させる危険性
直接原価基準では、短期的には弾力的な価格決定に役立ちます。しかし、不働能力を稼働させるために短期的な視点で価格決定を行うと、競合他社との値下げ競争に陥る危険性があり、長期的に競争が激化しかねません。
なお、販売価格は販売数量に影響を与えるため、原価を基準に価格決定を行う会計モデルには、堂々巡りの問題が付きまといます。
全部原価法でも、部分原価法でも、単位原価を決定しなければ目標価格を決定できません。単位原価は製造販売量の影響を受けるので、まず販売量がわからなければなりません。しかし、販売量は販売価格に左右されるので、目標価格が決まらなければ販売量を予測できません。
ただ、直接原価基準では、原価を変動費と固定費に分離するので、固定費を含めた単位当たり総原価が製造販売量の影響を受けやすい全部原価法と比較して、堂々巡りの問題は薄まると考えられます。