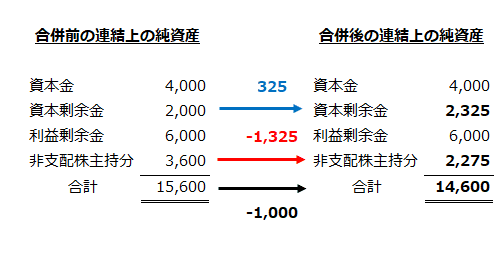同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理の具体例(合併対価が吸収合併存続会社の株式と現金等の財産である場合-結合当事企業(親会社)が受け取った現金等の財産の簿価が吸収合併消滅会社の株主資本の額を上回る場合)
ここでは、同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が吸収合併存続会社の株式と現金等の財産である場合-結合当事企業(親会社)が受け取った現金等の財産の簿価が吸収合併消滅会社の株主資本の額を上回る場合)について具体例を用いて解説します。
前提条件
- 公開会社の甲社(3月決算会社)は、x1年3月31日に乙社の株式と丙社の株式を取得し子会社としました。
- 甲社は、乙社の持分の80%(80株)を2,400千円で取得しています。乙社の発行済株式数は100株です。なお、x1年3月31日の乙社の個別貸借対照表は以下の通りです。
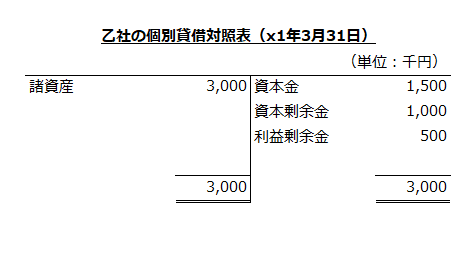
- 甲社は、丙社の持分の60%(60株)を3,000千円で取得しています。丙社の発行済株式数は100株です。なお、x1年3月31日の丙社の個別貸借対照表は以下の通りです。
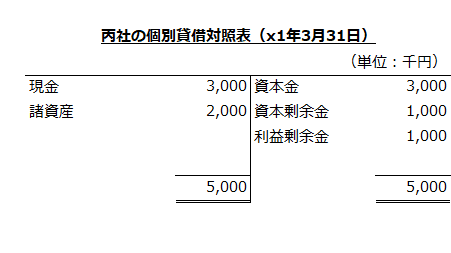
- x2年3月期の乙社と丙社の当期純利益は以下の通りです。
乙社=1,000千円
丙社=2,000千円 - x2年4月1日に丙社は、乙社を吸収合併しました。
- 丙社は、乙社の株主に対して現金5,000千円(甲社に4,000千円、乙社の非支配株主に1,000千円)を支払います。
また同時に新株60株を交付し、甲社は48株、乙社の非支配株主は12株を受け取ります。これにより丙社の株主の持分比率は以下のようになりました。
甲社=67.5%
旧乙社の非支配株主=7.5%
合併前からの丙社の非支配株主=25.0% - 甲社の合併期日の前日(x2年3月31日)の個別貸借対照表は以下の通りです。
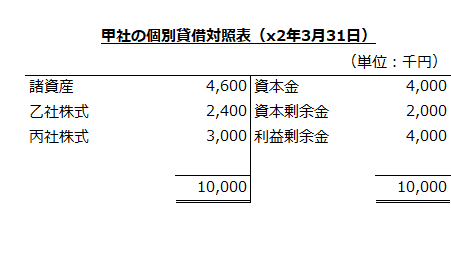
- 乙社の合併期日の前日(x2年3月31日)の個別貸借対照表は以下の通りです。なお、乙社の諸資産の適正な帳簿価額(株主資本)は4,000千円、企業の時価は11,000千円です。
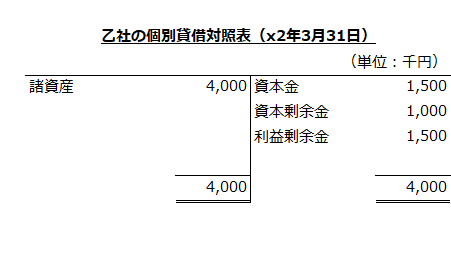
- 丙社の合併期日の前日(x2年3月31日)の個別貸借対照表は以下の通りです。なお、丙社の諸資産の適正な帳簿価額(株主資本)は7,000千円、企業の時価は21,000千円です。
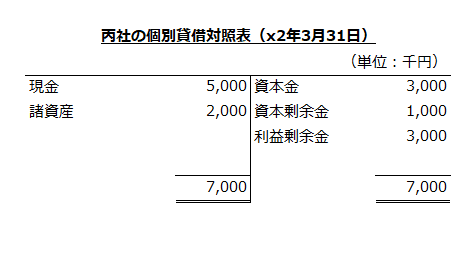
- 丙社は、吸収合併により株主資本が増加する場合、払込資本の全てをその他資本剰余金とします。
会計処理目次
- x2年3月期の甲社の連結貸借対照表
- x2年4月1日の甲社の個別財務諸表上の会計処理
- x2年4月1日の乙社の個別財務諸表上の会計処理
- x2年4月1日の丙社の個別財務諸表上の会計処理
- x2年4月1日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
x2年3月期の甲社の連結貸借対照表
甲社は、x1年3月31日に乙社の株式と丙社の株式を取得し、両社を子会社としました。その後、x2年4月1日に乙社を吸収合併消滅会社、丙社を吸収合併存続会社とする吸収合併をさせています。
x1年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
x1年3月31日に甲社は、乙社株式80株(持分比率80%)を2,400千円で取得しています。また、丙社株式60株(持分比率60%)も3,000千円で取得しています。
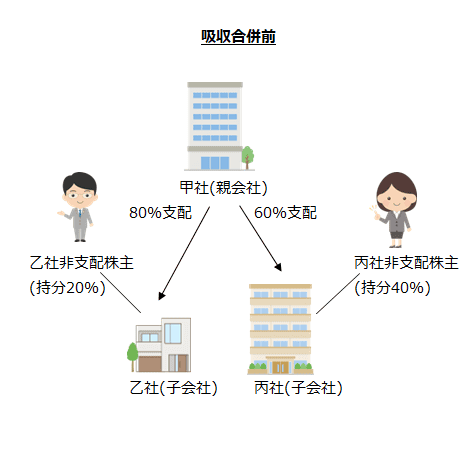
乙社資本の甲社持分と非支配株主持分の計算
甲社の持分比率は80%、非支配株主の持分比率は20%なので、以下の計算より、甲社持分は2,400千円、非支配株主持分は600千円となります。
- 甲社持分
=乙社の資本×甲社の持分比率
=3,000千円×80%
=2,400千円 - 非支配株主持分
=乙社の資本×非支配株主の持分比率
=3,000千円×20%
=600千円
のれん(乙社分)の算定
甲社の乙社株式の取得原価は2,400千円、甲社持分は2,400千円なので、甲社の連結財務諸表に計上されるのれんはゼロになります。
- のれん
=甲社の投資額-甲社持分
=2,400千円-2,400千円
=0
投資と資本の相殺消去(乙社分)
乙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係を図示すると以下のようになります。
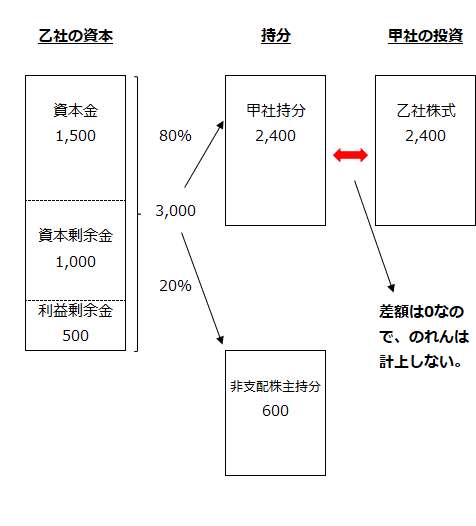
以上より、x1年3月31日の甲社の連結財務諸表作成のための甲社の投資と乙社の資本の相殺消去の会計処理は以下のようになります。
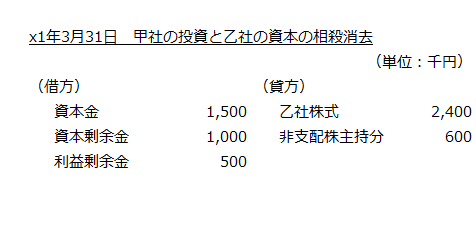
丙社資本の甲社持分と非支配株主持分の計算
甲社の持分比率は60%、非支配株主の持分比率は40%なので、以下の計算より、甲社持分は3,000千円、非支配株主持分は2,000千円となります。
- 甲社持分
=丙社の資本×甲社の持分比率
=5,000千円×60%
=3,000千円 - 非支配株主持分
=丙社の資本×非支配株主の持分比率
=5,000千円×40%
=2,000千円
のれん(丙社分)の算定
甲社の丙社株式の取得原価は3,000千円、甲社持分は3,000千円なので、甲社の連結財務諸表に計上されるのれんはゼロになります。
- のれん
=甲社の投資額-甲社持分
=3,000千円-3,000千円
=0
投資と資本の相殺消去(丙社分)
丙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係を図示すると以下のようになります。
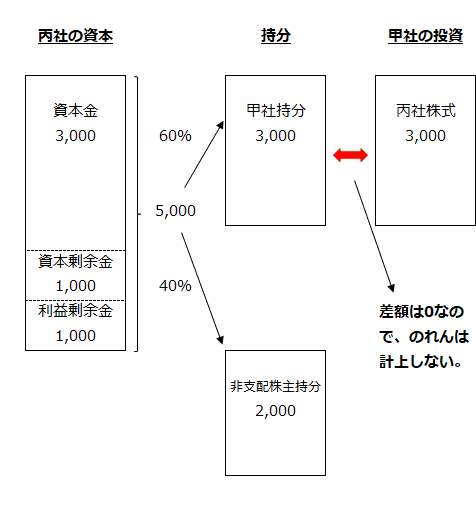
以上より、x1年3月31日の甲社の連結財務諸表作成のための甲社の投資と丙社の資本の相殺消去の会計処理は以下のようになります。
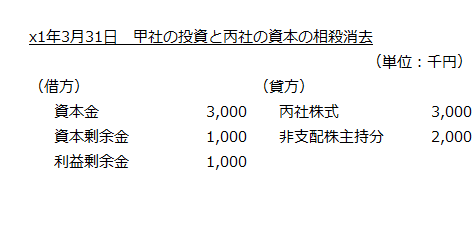
x2年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
甲社、乙社、丙社の個別貸借対照表を単純合算
x2年3月31日の甲社、乙社、丙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。
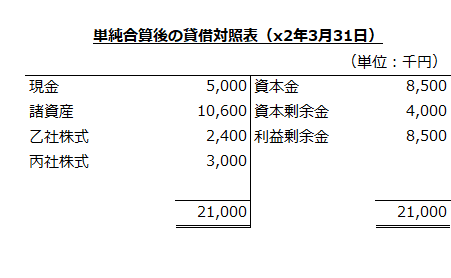
開始仕訳
x1年3月31日の連結財務諸表上の会計処理の投資と資本の相殺消去(乙社分)と投資と資本の相殺消去(丙社分)の会計処理を開始仕訳として起こします。
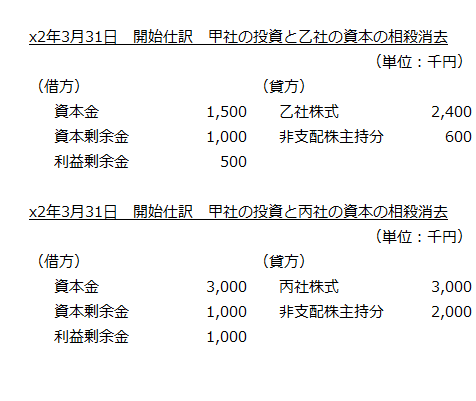
乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分
x2年3月期の乙社の当期純利益は1,000千円だったので、その20%を非支配株主持分に按分します。
- 非支配株主持分に按分する当期純利益
=当期純利益×非支配株主の持分比率
=1,000千円×20%
=200千円
よって、乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分する会計処理は以下のようになります。
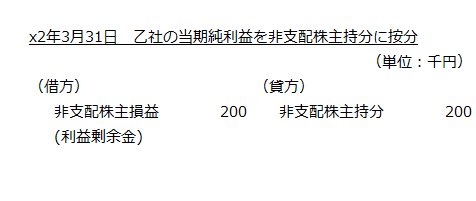
丙社の当期純利益を非支配株主持分に按分
x2年3月期の丙社の当期純利益は2,000千円だったので、その40%を非支配株主持分に按分します。
- 非支配株主持分に按分する当期純利益
=当期純利益×非支配株主の持分比率
=2,000千円×40%
=800千円
よって、丙社の当期純利益を非支配株主持分に按分する会計処理は以下のようになります。
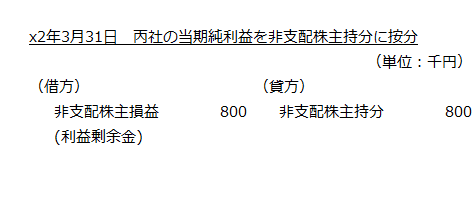
x2年3月期の連結貸借対照表
以上の会計処理を単純合算後の貸借対照表に反映させた甲社の連結貸借対照表は以下の通りです。
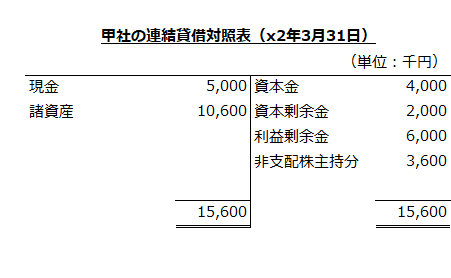
x2年4月1日の甲社の個別財務諸表上の会計処理
x2年4月1日に丙社は乙社を吸収合併し、その対価として現金5,000千円(甲社に4,000千円、乙社の非支配株主に1,000千円)を支払うとともに新株60株(甲社に48株、旧乙社の非支配株主に12株)を交付しています。当該吸収合併により、丙社に対する持分比率は、甲社が67.5%、旧乙社の非支配株主が7.5%、合併前からの丙社の非支配株主が25.0%となっています。
甲社は、吸収合併後も丙社を67.5%支配しています。したがって、当該企業結合は、結合当事企業(または事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配されていることから、支配が一時的でなければ共通支配下の取引となります。
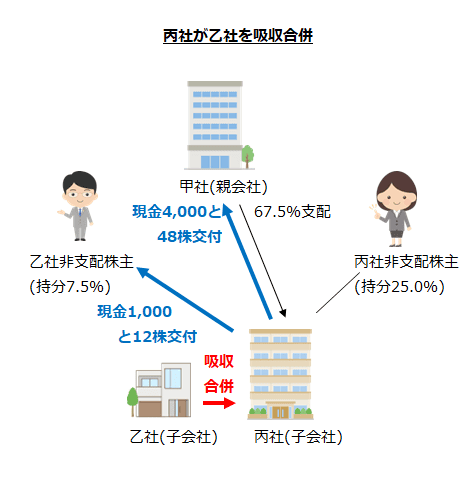
丙社株式の取得
甲社が受け取った現金等の財産は、原則として、移転前に付された適正な帳簿価額により計上します。当該価額が乙社の株式に係る適正な帳簿価額を上回る場合、原則として当該差額を交換利益として認識し、丙社株式の取得原価はゼロとします(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第252項)。
甲社が受け取った現金は4,000千円、乙社株式の適正な帳簿価額は2,400千円なので、差額1,600千円が交換利益となり、丙社株式の取得原価はゼロとなります。
よって、甲社の個別財務諸表上の会計処理は以下のようになります。
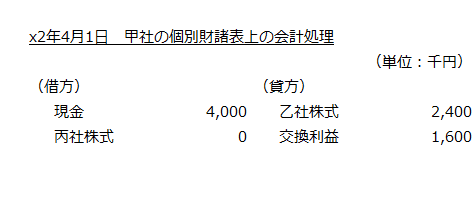
x2年4月1日の甲社の個別貸借対照表
以上より、吸収合併後(2年4月1日)の甲社の個別貸借対照表は以下のようになります。なお、交換利益1,600千円は、利益剰余金に含めています。また、丙社株式は、吸収合併前から保有している3,000千円と吸収合併で取得した部分(ゼロ)を分けて表示しています。
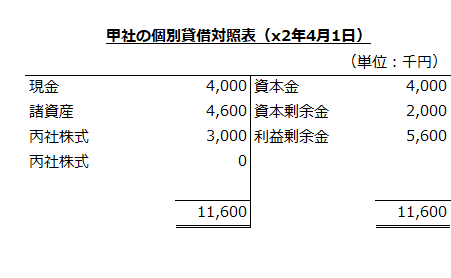
x2年4月1日の乙社の個別財務諸表上の会計処理
吸収合併消滅会社である乙社は、合併期日の前日(x3年3月31日)に決算を行い、資産および負債の適正な帳簿価額を算定します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第250項)。
乙社消滅の会計処理
乙社は丙社に吸収合併されるため消滅します。よって、乙社の個別財務諸表上の会計処理は以下のようになります。
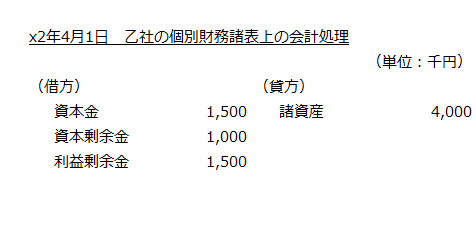
x2年4月1日の乙社の個別貸借対照表
以上より、吸収合併後(2年4月1日)の乙社の個別貸借対照表は以下のようになります。
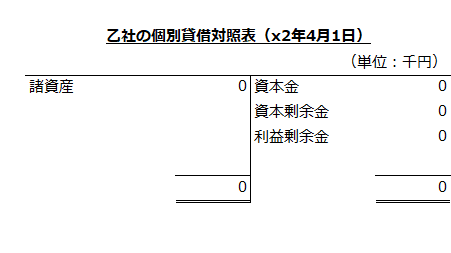
x2年4月1日の丙社の個別財務諸表上の会計処理
吸収合併存続会社である丙社は、乙社から受け入れる資産および負債を合併期日の前日の適正な帳簿価額により計上します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第251項(1))。また、乙社の適正な帳簿価額による株主資本の額から合併の対価として支払った現金等の財産の移転前に付された適正な帳簿価額を控除した額がマイナスとなる場合は、払込資本をゼロとし、のれんを計上します(同適用指針第251項(2)①)。
本事例では、合併期日の前日(x2年3月31日)における乙社の適正な帳簿価額による株主資本の額は4,000千円、丙社が乙社の株主に支払った現金は5,000千円です。したがって、両社の差額1,000千円について、のれんを計上します。
- のれん
=取得の対価-乙社の株主資本
=5,000千円-4,000千円
=1,000千円
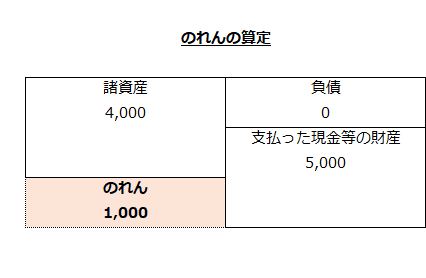
よって、丙社の個別財務諸表上の会計処理は以下のようになります。
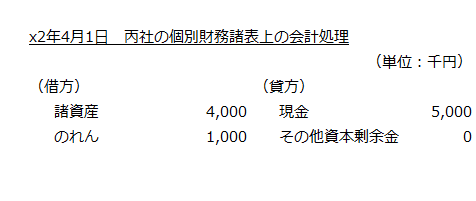
x2年4月1日の丙社の個別貸借対照表
以上より、吸収合併後(2年4月1日)の丙社の個別貸借対照表は以下のようになります。
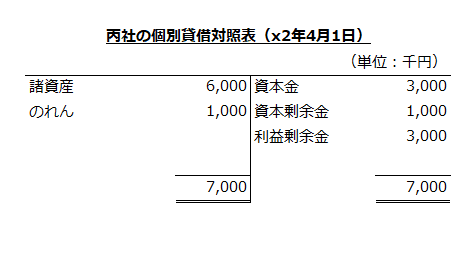
x2年4月1日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
甲社と丙社の個別貸借対照表を単純合算
吸収合併後(x2年4月1日)の甲社と丙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。
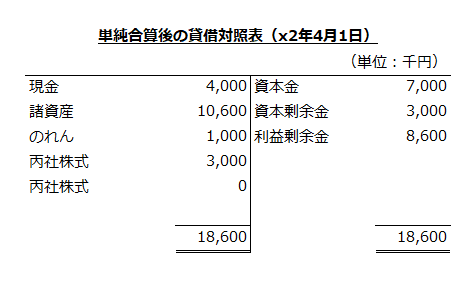
開始仕訳
x2年3月31日における甲社の連結財務諸表上の会計処理を開始仕訳として起こします。
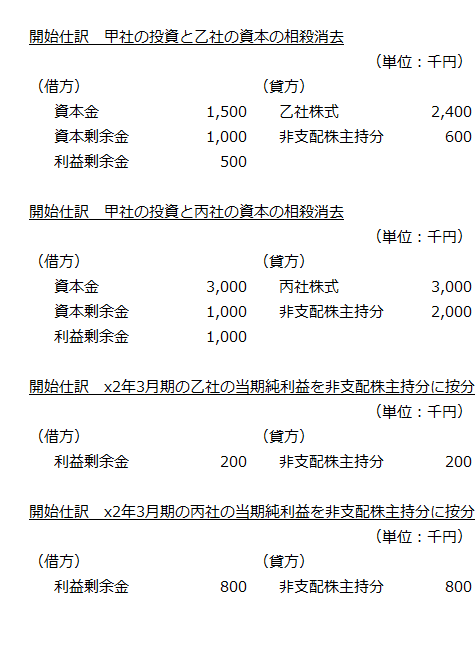
乙社株式に関する開始仕訳の振戻し
乙社は丙社に合併されたため、乙社株式に関する開始仕訳を振り戻します。会計処理は以下の通りです。
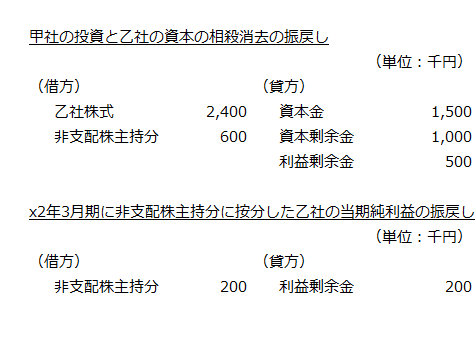
開始仕訳と乙社株式に関する開始仕訳の振戻しを反映した後の貸借対照表
開始仕訳と乙社株式に関する開始仕訳の振戻しを反映した後の貸借対照表は以下の通りです。
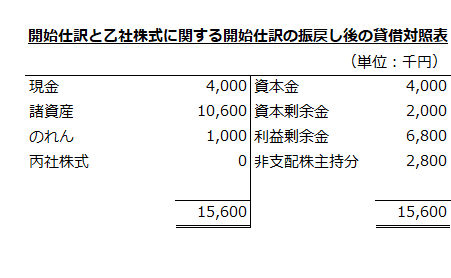
甲社の持分変動
吸収合併前(x2年3月31日)の甲社の持分比率は以下の通りでした。
- 乙社
=80%(甲社持分=3,200千円、非支配株主持分=800千円) - 丙社
=60%(甲社持分=4,200千円、非支配株主持分=2,800千円)
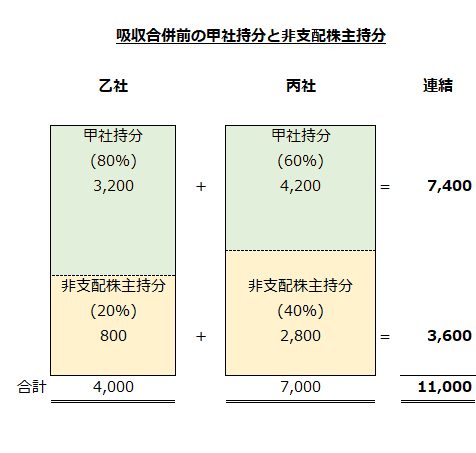
そして、吸収合併後(x2年4月1日)の甲社の持分比率は以下のように変動しています。
- 乙社
=67.5%(甲社持分=0、非支配株主持分=0) - 丙社
=67.5%(甲社持分=4,725千円、非支配株主持分=2,275千円)
したがって、乙社に対する持分は12.5%減り、丙社に対する持分は7.5%増えています。
なお、丙社は、乙社の株主に株式を交付していますが、対価として支払った現金等の財産の適正な帳簿価額が乙社(吸収合併消滅会社)の株主資本の額を上回っているため、払込資本(その他資本剰余金)の増加額はゼロとなっています。そのため、吸収合併後の乙社に対する甲社持分も非支配株主持分もゼロとなります。
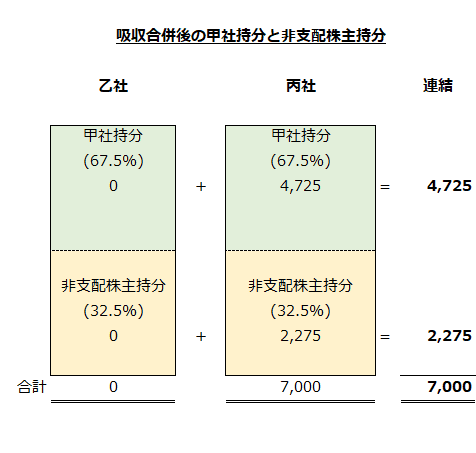
開始仕訳と乙社株式に関する開始仕訳の振戻しを反映した後の貸借対照表に計上されている非支配株主持分は2,800千円、吸収合併後の連結貸借対照表に計上されるべき非支配株主持分は2,275千円なので、両者の差額525千円を調整します。
乙社の非支配株主持分の調整
乙社株式に関する開始仕訳を振り戻しているため調整は不要です。
丙社の非支配株主持分の調整
開始仕訳と乙社株式に関する開始仕訳の振戻しを反映した後の貸借対照表に計上されている非支配株主持分2,800千円は、吸収合併前の丙社の非支配株主持分です。
吸収合併後の丙社の非支配株主持分2,275千円との差額525千円は、甲社の持分比率が60%から67.5%に増えたことによる甲社持分の増加額と一致します。
- 甲社の持分の増加額
=丙社の株主資本×(合併後の甲社持分-合併前の甲社持分)
=7,000千円×(67.5%-60%)
=525千円
非支配株主持分の減少額
以上より、丙社の非支配株主持分の減少額525千円を開始仕訳と乙社株式に関する開始仕訳の振戻しを反映した後の貸借対照表に計上されている非支配株主持分2,800千円から差し引くと吸収合併後の連結貸借対照表に計上されるべき非支配株主持分2,275千円と一致します。
よって、吸収合併後の連結財務諸表の作成における非支配株主持分の調整額は525千円になります。
持分変動
甲社の丙社に対する持分比率は吸収合併前の60%から67.5%に増えています。それにより、甲社の丙社に対する持分は吸収合併前の4,200千円から4,725千円に増加しており、両者の差額525千円が丙社に対する持分変動による増加額となり、当該価額は非支配株主持分の減少額525千円と一致します。
当該丙社に対する持分変動による増加額525千円を資本剰余金に計上します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第253項)。
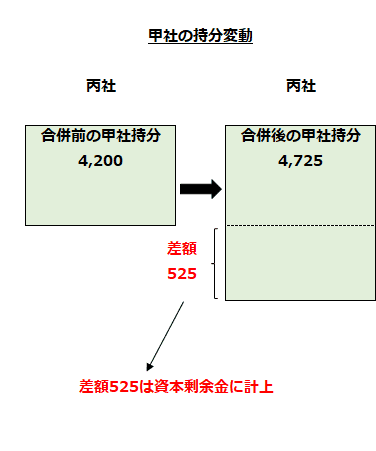
甲社の持分変動の会計処理
よって、甲社の持分変動の会計処理は、以下のようになります。
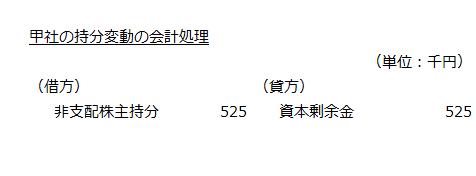
取得後剰余金の認識、交換利益の修正、のれんの消去
取得後剰余金の認識
乙社のx2年3月31日の利益剰余金(当期純利益)1,000千円のうち、甲社の持分は80%だったので、x2年3月31日の連結貸借対照表上の利益剰余金には800千円の取得後剰余金が含まれています。
- 乙社における甲社分の取得後剰余金
=乙社のx2年3月期の当期純利益×甲社持分
=1,000千円×80%
=800千円
したがって、吸収合併後(x2年4月1日)の連結財務諸表上、取得後剰余金800千円を認識する必要があります。
交換利益の修正
吸収合併消滅会社の株主(親会社)の個別財務諸表上認識された交換利益は、親会社の連結財務諸表上、「連結財務諸表に関する会計基準」における未実現損益の消去に準じて処理します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第253項)。
本事例では、親会社である甲社が、吸収合併により個別財務諸表上で1,600千円の交換利益を認識しているので、連結財務諸表上、これを取り消します。
取得後剰余金の認識と交換利益の修正を開始仕訳と乙社株式に関する開始仕訳の振戻し後の貸借対照表に反映させると、吸収合併後(x2年4月1日)の利益剰余金は6,000千円となり、吸収合併直前(x2年3月31日)の利益剰余金6,000千円と一致します。
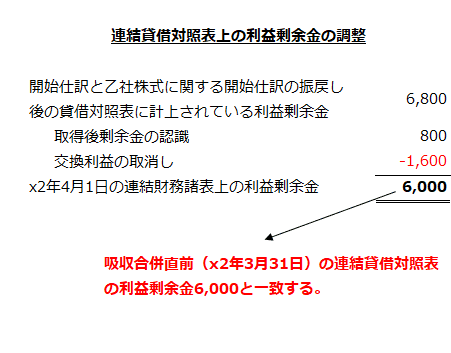
のれんの消去
丙社の個別財務諸表上で認識したのれん1,000千円を消去します。
また、甲社は、乙社を吸収合併前は80%支配していたので、消去したのれん1,000千円のうち20%(100%-80%)の200千円が親会社の持分変動により生じた差額となり、資本剰余金に計上します。
取得後剰余金の認識、交換利益の修正、のれんの消去の会計処理
以上より、取得後剰余金の認識、交換利益の修正、のれんの消去の会計処理は以下のようになります。
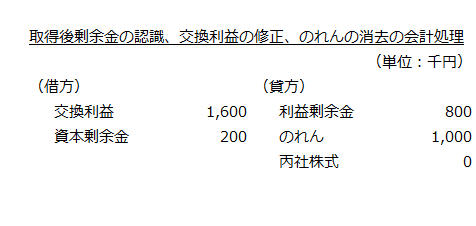
吸収合併後の連結貸借対照表
よって、吸収合併後の甲社の連結貸借対照表は以下のようになります。
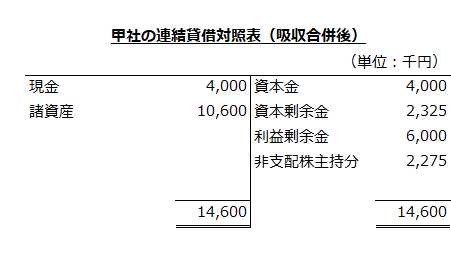
非支配株主持分は、吸収合併前の3,600千円から2,275千円に減少しています。差額1,325千円は、吸収合併前の乙社の非支配株主持分800千円と丙社の非支配株主持分が2,800千円から2,275千円に減少したことによって生じた甲社の持分変動525千円との合計1,325千円と一致します。吸収合併後は、丙社の非支配株主持分2,275千円(32.5%)だけが連結貸借対照表に計上されます。
資本剰余金は、2,000千円から2,325千円に増加しています。差額325千円は、非支配株主持分から甲社持分に振り替えた甲社の持分変動525千円からのれん1,000千円のうち20%の200千円(甲社の持分変動による差額)を差し引いた325千円と一致します。
合併前の連結上の純資産の合計15,600千円と合併後の連結上の純資産の合計14,600千円との差額1,000千円は、乙社の非支配株主に支払った現金1,000千円と一致します。